この記事は広告を含みます。
詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
目次

唯一無二の個性と愛らしさがあるミックス犬ですが、見た目のかわいさだけで選ぶと「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうことも。
この記事では、ミックス犬ならではのデメリットや注意点、後悔しないための選び方をわかりやすく解説しています。
飼い始める前に知っておきたい大切なポイントをぜひチェックしてください。
そもそも「ミックス犬」ってどんな犬?

異なる犬種を掛け合わせて生まれるミックス犬。「チワプー」や「マルプー」などの愛称で人気を集めていますよね。
ここでは、雑種犬との違いや注目されている理由について、わかりやすく紹介します。
ミックス犬の特徴とは?雑種犬との違い
「ミックス犬」とは、異なる純血種同士を掛け合わせて意図的に交配された犬を指します。
たとえば、「チワワ×トイ・プードル」「マルチーズ×トイ・プードル」のように人気犬種を組み合わせた犬が多く、「チワプー」や「マルプー」などの愛称で呼ばれていますよね。
個体差はありますが、予測できない見た目や性格もミックス犬の魅力のひとつとされ、近年注目されているのです。
一方、「雑種犬」は親犬の犬種が不明、もしくは何世代にもわたり複数の犬種が混ざっている犬のことを指します。
つまり、チワワとトイ・プードルの子犬として販売されている犬はミックス犬、保護犬で犬種不明の場合は雑種犬ということ。
また、ミックス犬は「デザイナーズドッグ」と呼ばれることもありますが、これは見た目のかわいさや性格のよさをねらって交配された犬という意味合いがあり、ファッション的なニュアンスを含むこともあります。
近年人気が高まっている理由
SNSやテレビなどで紹介されることでミックス犬のかわいらしさが広まり、人気が急上昇しました。
また、トイ・プードルやチワワ、マルチーズなどの人気犬種を掛け合わせた「小型でおしゃれな犬」として、都市部を中心に需要が高まっているのです。
さらに、「病気に強い」「抜け毛が少ない」「吠えにくい」などといった“いいとこどり”なイメージが広まったことで、初心者にも飼いやすいと思われた背景から人気が継続しているといえるでしょう。
実際はそうした特徴が必ずしも保証されるわけではないため、不確実なうわさや見た目のかわいさだけで選ぶことはおすすめしません。
ミックス犬のデメリット5選
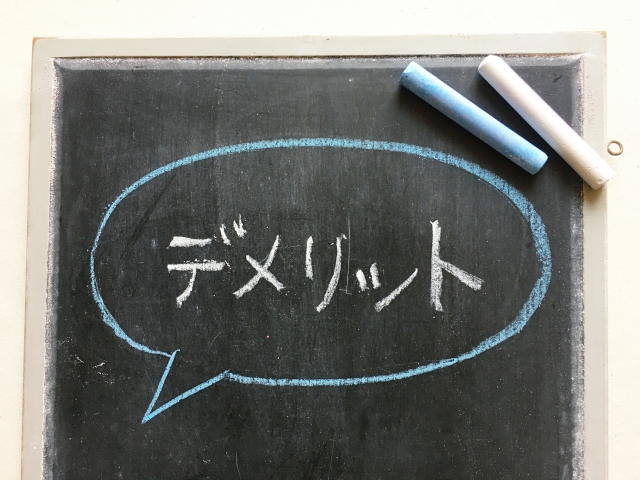
ミックス犬を飼いたいと考えているならば、飼い始める前にミックス犬のデメリットを把握しておくことが大切です。
ここでは、ミックス犬のデメリットを詳しく紹介します。
成長後のサイズや性格が予測しづらい
ミックス犬は、異なる犬種の“いいとこどり”を期待されがちですが、実際には成長してみないとわからない部分がとても多いといえます。
たとえば、子犬のときは小柄でおとなしそうだったのに、成犬になったら想像以上に大きくなったり、活発すぎてついていけなくなったり……ということもよくある話。
親犬のどちらの性質が強く出るかは、生まれてくる子によってバラバラなのです。
体格も性格も予測しづらいといえるでしょう。
遺伝病のリスクが2倍になる可能性がある
「ミックス犬は雑種だから健康!」というイメージを持っていませんか?
確かに、遺伝的な弱点を打ち消し合うことで、病気になりにくい個体もいます。
しかし一方で、親犬それぞれの持つ遺伝病のリスクを“両方”受け継ぐ可能性もあるのです。
たとえば、チワワが持ちやすい膝のトラブルと、トイ・プードルがなりやすい目の病気、両方を持って生まれてしまうことも。
健康そうに見えても、実は気をつけるべきポイントが多いといえるでしょう。
その際、愛犬が滑って転倒したり、関節に負担をかけないようペット用床材を使うなど、日頃から足元の環境にも気を配ることが大切です。
▼おすすめ商品はこちら
高機能フローリング「ワンラブフロアV」
機能性床材「リフェイスタイル」
親の特徴が極端に出ることがある|個体差が大きい
ミックス犬は、異なる犬種の親から生まれるため、兄弟であっても見た目や性格が大きく異なることがあります。
一方がチワワの特徴、もう一方がトイ・プードルの特徴を色濃く受け継ぐと、兄弟なのに「本当に同じ犬種?」と驚くほど違う印象になることも。
「この子の兄弟だから、似ているはず!」と思いがちですが、ミックス犬は兄弟でも全然違う顔つきや毛色、性格になることがあります。
Aはおとなしいけど、Bはとにかくやんちゃ。
Cは抜け毛が多いけど、Dは抜け毛が少ない…なんてことも。
ひとことで「ミックス犬」といっても個体差がかなり大きいので、事前に「こういう犬種だから大丈夫」と思い込まないことが大切です。
しつけの難しさ・育てにくさを感じるケースがある
性格が予測しにくいということは、しつけの方向性も定まりにくいということでもあります。
純血種なら「この犬種はこういう傾向があるから、こう育てよう」と見通しを立てやすいのですが、ミックス犬はそれが難しいといえるのです。
たとえば、社交的な犬種と警戒心が強い犬種のミックスだった場合でも、「知らない人が苦手」「吠えやすい」など一方の性質が強く出ることもあります。
一緒に過ごしながら少しずつ性格を把握して、時間をかけて向き合っていく覚悟が必要です。
その際、外の物音や気配に反応して吠えやすい子には、防音対策として内窓リフォームや、遮熱・断熱・遮音・防音・消臭・空気質改善効果のある住宅塗料を使うなど、室内環境を整えることも効果的です。
▼おすすめ商品はこちら
内窓リフォーム「プラマードU 」
住宅用塗料「ガイナ」
「いいとこどり」は幻想?繁殖の裏事情
「ミックス犬は、親犬のよいところだけを受け継いでるから安心」と思われがちですが、実際には「いいとこどり」ではなく、「どちらの欠点も受け継ぐ可能性」も十分あるということを忘れてはいけません。
さらに残念ながら、人気のミックス犬を商業的に乱繁殖しているブリーダーや業者もいます。
親犬の健康管理が十分でなかったり、無理な掛け合わせをしたりすることで、子犬が生まれつき弱かったり、性格に問題を抱えていたりするケースも。
見た目のかわいさや流行だけで選ぶのではなく、その子の背景やブリーダーの姿勢にも目を向けてほしいなと思います。
ミックス犬を迎える前に知っておくべき3つの現実

ミックス犬は見た目の可愛さや個性で注目される一方、その背景にはあまり語られない繁殖や販売の問題があります。
ここでは、飼う前に知っておきたい3つの視点から現状を見ていきましょう。
無計画な繁殖や「流行り重視」の背景
近年、SNSやテレビで話題になり、ミックス犬が急速に人気を集めています。
「チワプー」や「マルプー」などのブランド化された呼び名も、ブームを後押ししているといえるでしょう。
その一方で、「かわいいから」「売れるから」といった理由だけで繁殖が繰り返されるケースも少なくありません。
見た目の流行にばかり注目が集まり、性格や健康状態が後回しになることも。
本来は命を扱う重大なことなのに、商業的な視点だけで交配されてしまうのは、大きな問題です。
繁殖管理が甘いブリーダーも存在する
すべてのブリーダーがそうではありませんが、中には「健康状態の確認をせずに交配」「親犬の遺伝的疾患に関する知識が乏しい」といった、ずさんな管理をしているブリーダーもいます。
特にミックス犬は、親犬それぞれの遺伝病のリスクを受け継ぐ可能性もあるため、慎重な繁殖管理が求められます。
しかし現実には、そのリスクが十分に説明されないまま販売されていることもあるのです。
購入を考えるなら、きちんと親犬の健康状態や飼育環境を確認できる、信頼できるブリーダーから迎えることが大切です。
「ペットショップでの衝動買い」が生む飼育放棄
ショーケースの中で無邪気に動く子犬を見て、「この子、うちに迎えたい!」と衝動的に買ってしまう人も少なくありません。
しかし、見た目のかわいさだけで判断してしまうと、後から「思っていたより大変」「性格が合わない」と感じることも。
衝動買いの結果、数日〜数週間で飼育を放棄されるミックス犬も現実にいます。
特に、ペットショップでの販売は飼育環境や繁殖背景が見えにくいため、慎重な判断が必要です。
ミックス犬を選ぶときのチェックポイント

見た目がかわいくて個性豊かなミックス犬。でも、選び方を間違えると後悔してしまうことも。
ここでは、迎える前にしっかり確認しておきたい大切なポイントを紹介します。
親犬の情報を必ず確認する
どんな性格や体質になるのかをある程度予測するには、親犬の情報がとても重要です。
たとえば、「どんな犬種の組み合わせなのか」「親犬の性格や健康状態はどうか」といった情報があれば、その子の将来を想像しやすくなります。
特に体格や運動量、かかりやすい病気などは、親犬からの遺伝が大きく影響することも。
「どんな子に育つんだろう?」という楽しみはあるけれど、安心して迎えるためにも親犬のプロフィールはしっかり確認しましょう。
信頼できるブリーダーや団体を選ぼう
ミックス犬はペットショップでもよく見かけますが、できればブリーダーや保護団体など、犬の背景をきちんと説明してくれるところから迎えるのが安心です。
特に信頼できるブリーダーは、犬の健康管理や社会化にもしっかり取り組んでいます。
繁殖環境が清潔で、犬たちがのびのびと暮らしているかどうか、実際に見学できるのも大きなポイント。
「かわいいから」という理由だけで衝動的に決めず、その子がどんな環境で育ったかを知ることが、のちのトラブル防止にもつながります。
見た目だけで決めない!性格・体質を重視する
ミックス犬は、つい「この見た目が好き!」と決めてしまいがちです。
しかし、暮らしていく上で大切なのは、見た目以上に性格や体質であることを忘れてはいけません。
たとえば、見た目は小さくておとなしそうでも、実は活発で運動が大好きだったり、逆に社交的に見えて人見知りが強かったりすることもあります。
「自分のライフスタイルに合っているか」「家族と相性がよさそうか」など、見た目以外の要素もよく見てあげてくださいね。
病歴・遺伝病の検査状況を確認することも重要
最後に、健康面の確認も忘れずに。ミックス犬は雑種よりも、遺伝的な病気を受け継ぐ可能性が高い場合もあります。
信頼できるブリーダーや保護団体であれば、親犬の遺伝病の検査結果を提示してくれることが多く、ワクチン接種歴や病歴についてもしっかり把握しています。
「健康そうに見えるから大丈夫」と思わず、後悔しないためにも、しっかり確認しておきましょう。
ミックス犬のデメリットを理解して迎えることが大切

ミックス犬の魅力はたくさんありますが、同時に見過ごせないデメリットもあります。
「家族として迎える」という責任を持つためには、かわいさだけで決めず性格や健康面、将来のケアまでしっかり調べることが大切。
後悔しないためにも、冷静な目で事前リサーチを怠らず、納得したうえでお迎えしましょう





